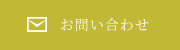お金がなくても墓じまいはできる?費用相場と対処法を解説2025.07.23 コラム
墓じまいをしたいけど、「費用が不安で墓じまいに踏み切れない」という声は少なくありません。本記事では、費用の内訳から実際の対処法まで、専門的な視点で解説します。限られた予算の中でも墓じまいをする方法について、わかりやすく説明します。
そもそも墓じまいとは?

近年「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、その意味や背景を正確に理解している方は、まだ少ないかもしれません。まずは、墓じまいの意味と、それを選ぶ人が増えている社会的背景を整理してみましょう。
墓じまいの意味と背景
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、遺骨を新たな場所に移す一連の手続きのことです。背景には、少子化や核家族化の進行、都市部への人口集中といった社会構造の変化があります。
後継者不在や遠方の居住によって墓の管理が困難になるケースが増え、放置される前に墓じまいを検討する人が増えています。
永代供養や合祀墓などの新たな選択肢
墓じまいをした後、遺骨を納める方法として注目されているのが永代供養や合祀墓です。永代供養では、寺院や霊園が責任を持って供養と管理を継続してくれるため、後継者がいない場合でも安心です。
とくに合祀墓は費用が抑えられ、他の方と一緒に埋葬されることで管理の手間も軽減されます。これらは「お金がない」という状況でも選びやすい選択肢の一つといえるでしょう。
墓じまいに必要な費用と内訳
墓じまいを検討する上で、多くの人が気にするのが費用です。ここでは、墓じまいに伴って必要となる代表的な費用項目と、その目安を項目ごとに解説します。
遷仏法要・墓石撤去・遺骨の取り出し
墓じまいでは、まず「遷仏法要(閉眼供養)」が行われます。これは僧侶に読経を依頼する法要で、費用は地域や宗派によって異なります。お布施は、3万~5万円程度が相場です。
実際には「お車代」や「御膳料」が別途必要になる場合もあり、お布施が7万円を超えることもあります。また、遷仏法要の際には親族が集まることも多く、スケジュール調整にも配慮が必要です。
その後、遺骨を取り出し、墓石を解体・撤去する作業が行われます。撤去作業は重機を使用するため、搬入経路や近隣への配慮も必要です。墓石の大きさや立地条件、地域による処分費の違いによって、作業費用は10万円〜30万円程度と大きな幅があります。
離壇料・行政手続き・書類準備費用
お墓が寺院の敷地内にある場合には、「離壇料」を求められることがあります。これはお寺との関係を終了する際に納める謝礼で、相場は5万〜20万円ほどです。離壇料には明確な規定がないため、判断に迷う場合は他の檀家に聞いてみるのも、一つの方法です。
また、墓じまいには「改葬許可申請」という行政手続きが必要で、市区町村の役所で改葬許可証を取得する必要があります。この手続きには、使用中の墓地の管理者からの「埋葬証明書」と、新たな納骨先の「受入証明書」が必要です。
これらの書類は自分でも準備できますが、難しそうだと感じる方は、行政書士に依頼できます。行政書士への依頼費用は、おおむね3〜5万円が目安です。
新たな納骨先と納骨時のお布施代
遺骨を新たに納める先としては、合祀墓や永代供養墓、樹木葬などさまざまな選択肢があります。合祀墓であれば3万~10万円程度で利用できるケースが多く、個別納骨型の永代供養墓では20万~50万円前後が一般的です。また、樹木葬には個別区画タイプと共同区画タイプがあり、費用や維持条件に差があります。
納骨時には再び僧侶に読経を依頼することがあり、その際のお布施として2万~5万円が必要になります。また、地域や宗派によっては、「納骨法要」として親族を招くこともあり、その費用も必要です。費用だけでなく、納骨のタイミングや方法についても、あらかじめ検討しておくことが大切です。
お金がないまま墓じまいを放置するリスクとは
費用の問題から墓じまいを先延ばししてしまうと、予期せぬリスクが発生することもあります。ここでは、放置することで起こりうる問題について整理します。
無縁仏・管理費の滞納・撤去通知
墓じまいを先延ばしすると、さまざまな問題を生じる可能性があります。もっとも懸念されるのが、墓地の管理費を滞納したまま長期間放置した結果、「無縁仏」とみなされてしまうケースです。
無縁仏になると、霊園や寺院によっては墓石に「撤去予告」の札が貼られたり、掲示板に通告されたりします。これにより親族に迷惑が及ぶこともあるため、早めの対処が求められます。
さらに注意すべきなのは、管理費滞納が続くと、霊園や自治体によっては訴訟や強制撤去の手続きが取られる場合もあることです。行政指導や裁判所を通じた通知が来ると、親族にまで連絡が届くことになり、精神的な負担も大きくなるでしょう。
また、撤去されたあとの墓石の処分費用や更地化費用を請求されることもあります。こうした負の連鎖を避けるためにも、墓じまいは早めの判断と行動が重要です。
相続やトラブルに発展する可能性
墓じまいの費用や方針について、事前に親族と話し合うことが重要です。相続のタイミングなどで意見が食い違い、トラブルに発展することがあるからです。
とくにお墓の名義人が亡くなった後の対応が遅れると、誰が責任を負うか明確でなくなる場合があります。結果として、親族で解体費用や管理費の負担を巡る争いの原因になりかねません。
資金がなくても墓じまいするための4つの対処法

費用がネックで墓じまいに踏み出せない方のために、資金を工面するための現実的な方法を紹介します。補助制度から納骨方法の見直しまで具体的に解説します。
自治体の補助金・助成制度の活用
墓じまいにかかる費用を少しでも抑えるためには、各自治体が提供する補助金制度を活用しましょう。
地域によっては、墓石の撤去費用や改葬先の準備費用の一部を助成してくれる制度があります。申請には改葬許可証や見積書、領収書の提出を求められることが多いため、事前に必要な書類を把握し、保管しておくことが大切です。
メモリアルローンや分割払いを利用
一括で支払うのが難しい場合、金融機関や石材店が提供するメモリアルローンを利用する方法があります。メモリアルローンとは「金融機関」「信販会社」などが供養や祭祀に限定したローンです。金利は通常のローンより低く、審査も通りやすい傾向があります。
墓石解体・撤去は複数業者に見積もり依頼する
墓石解体・撤去は、石材店や墓じまい専門業者によって、大きく費用が異なるケースもあります。そのため、1社だけで決めず、複数の業者から見積もりを取り比較することで、適正な工事費で契約が可能です。
また、工事費用の内訳や作業内容を明確に把握でき、不要な追加料金を避けることにもつながります。
合祀・樹木葬など安価な納骨先を選ぶ
納骨先の選択によっても費用は大きく変わります。合祀墓や樹木葬は、一般的な個別墓よりも費用を抑えられる選択肢です。
福善寺では高額な費用をかけずに供養ができるよう、個別納骨や合葬といった柔軟な方法を用意しています。
家族や親族に相談する際の注意点

墓じまいは、個人だけで完結するものではなく、家族や親族との話し合いが不可欠です。スムーズな合意形成のために、抑えておきたいポイントを解説します。
お金に関するトラブルを避ける方法
墓じまいの費用について、家族や親族に相談する方法もあります。一部費用を援助してもらえれば墓じまいができるケースもあります。その際は、必要な費用の内訳、見積書を共有することが大切です。
親族との認識共有と法的手続き
墓じまいは、親族間での合意が前提となります。勝手に進めてしまうと、トラブルになる可能性があります。改葬許可や離檀手続きのタイミング、納骨先の選定などについては、親族と事前に相談しましょう。
たとえば、兄弟間で事前に相談せずに墓石撤去を進めたことで、納骨先に対する意見が食い違い、後から感情的な対立に発展したケースもあるようです。このような事態を避けるには、LINEやメールでの報告ではなく、可能であれば実際に会ったり、電話したりするなど直接対話の場を設けることが望ましいでしょう。
また、名義人変更や相続に絡む法的手続きが必要なケースでは、司法書士や行政書士に早めに相談しておくことで、手続きの不備や相続争いの回避にもつながります。
墓じまいの費用が心配な方でも今すぐはじめられる準備
墓じまいに関心があるものの、経済的な事情で行動を起こせずにいる方は多いかもしれません。しかし、対応を後回しにすると、管理費の滞納や無縁仏化など、さらなる負担を招くリスクもあります。
まずは墓じまいの意味や費用を正しく理解し、自身の状況に合った計画を立てることが重要です。
補助金やローンの活用、費用の安い納骨方法の選定など、実行可能な選択肢は複数あります。加えて、家族や専門家との相談を通じて、客観的な意見やサポートを得ることも有効です。 宗派に関わらず受け入れてもらえる寺院もあるため、気軽に相談できる地元の寺院を探すことが第一歩です。