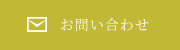永代供養に毎年の費用は必要?仕組みと注意点を専門家が解説2025.07.23 コラム
「永代供養は一括費用だけと思っていたのに、毎年支払いがあると聞いて不安」そう感じる方は少なくありません。実際には、一括で完結するプランもあれば、契約内容によっては追加費用が発生するケースもあります。
本記事では、永代供養の「毎年の費用」の有無や内訳、その注意点までわかりやすく解説します。
永代供養を検討中の方必見!毎年費用は必ず発生するのか?

「永代供養」と聞くと、一度支払えば済むと思っていたのに、後から追加費用がかかることもあると知って驚く方も少なくありません。しかし、実際には、永代供養の費用が一括で完結するプランと、毎年費用が発生するプランの両方が存在します。
ここでは、永代供養において毎年の費用支払いが「必ず」必要なのかを明らかにし、その仕組みと背景を解説します。
ご自身やご家族に合ったプランを選ぶために、「費用の発生理由」を把握することはとても重要です。後から「思っていたのと違った」と後悔しないためにも、事前にしっかり把握しておきましょう。
毎年払う必要がないプランもある
永代供養と聞くと「永代=ずっと払い続ける」と思われがちです。しかし、実際には一括払いで完結するプランが多く存在します。たとえば、合祀型の永代供養は、契約時にすべての費用を支払うスタイルで、追加の管理料や供養料はかからないケースが一般的です。
これはとくに樹木葬や納骨堂など、永代管理を前提とした埋葬方法に多く見られます。費用を明確にし、後々の負担を避けたい方にはこうした一括プランがおすすめです。
個別安置期間に応じて年払いが必要なケースも
一方で、一定期間個別に納骨するタイプの永代供養では、契約期間中に「年間管理料」や「護持会費」が発生することもあります。
たとえば、納骨堂や個別墓で10年間は個別安置、以降は合祀というプランでは、個別安置期間中に毎年の管理費を支払うことが必要です。これらは施設や宗派によって異なります。
そのため、「毎年費用が必要」になる条件をよく把握することが大切です。「永代供養」と一括りにせず、供養の内容をしっかり知っておきましょう。
毎年費用がかかるタイプの永代供養とは?

永代供養の中には、契約時の一括費用に加え、年間ごとに管理料や会費などの支払いが発生するタイプもあります。とくに都市部の納骨堂や寺院運営型の永代供養墓などでは、こうした毎年の費用が設けられているケースも少なくありません。
事前に「どのタイミングで、どんな費用が必要か」を把握しておくことが、予算の面でも安心につながります。
年間管理料が必要なケース(寺院型・納骨堂など)
寺院が運営する永代供養墓や、ロッカー型の納骨堂などでは、施設の維持費として「年間管理料」が必要になることがあります。これは主に共用スペースの清掃、設備の保守、水道光熱費などに充てられる費用で、年間1万円〜3万円程度が相場です。
とくに都市部の納骨堂ではこの傾向が強く、個別区画の維持にかかるコストとして定められています。契約書には「○年間分を一括納入」などと記載されることもあるため、支払い形態もあわせてよく見ておきましょう。
護持会費・年会費が必要なケースとは
寺院とのご縁を重視した永代供養では、檀家に近い立場として「護持会費」や「年会費」の支払いを求められる場合があります。
護持会とは、寺院を維持・支援する会員制度で、会費は年間5,000円〜1万円程度が一般的です。この費用は、法要の案内や年忌法要の開催など、寺院からのサポートに活用されます。
こうした費用が永代供養とは別に発生するかどうかも、事前の永代供養相談時に確認しておくべき重要なポイントです。
永代供養にかかる基本費用の内訳
永代供養の契約にあたって、最初に発生する費用は「基本費用」と呼ばれます。これは多くの場合、一括で支払うものであり、永代使用料や永代供養料をはじめとする必要不可欠な費用項目が含まれています。
しかし、施設や宗派によって含まれる内容や項目名が異なるため、「何にいくらかかるのか」を明確に理解することが重要です。
ここでは、永代供養にかかる基本費用の主な内訳について、名称・役割・相場を交えてわかりやすく解説します。
永代使用料・永代供養料の違いと意味
永代使用料とは、墓地や納骨スペースの「場所」を永代に渡って使うための費用です。一方、永代供養料は故人の供養を寺院が長期にわたり継続して行うことに対する対価になります。両者は混同されがちですが、性質が異なるため、契約時にはしっかり分けて確認することが重要です。
たとえば、ある霊園では永代使用料が20万円、永代供養料が10万円といったように、別枠で提示されます。もし、費用の名目が曖昧な場合には、内訳を明示してもらうようにしましょう。
納骨料・納骨読経料などの追加費用
永代供養の契約費用とは別に、実際に納骨する際には「納骨料」や「読経料」が必要になるケースがあります。納骨時に僧侶に読経を依頼する場合、そのお布施として3万円〜5万円程度を支払うのが一般的です。
想定外の出費に注意!永代供養で発生しうる追加費用とは?
永代供養の基本料金や年間管理費のほかに、「意外なタイミングで発生する追加費用」があることをご存じでしょうか。契約時には見落としがちですが、個別の法要や刻字などはオプション扱いとなることが多く、希望に応じて都度費用が必要になります。
ここでは、実際に発生しうる追加費用の内容とその金額感、注意すべき点について具体的に解説。あらかじめ知っておくことで、費用面も安心できます。
法要・お布施・戒名の費用
永代供養の基本料金には、三回忌や七回忌といった「年忌法要」の費用は含まれていないことが一般的です。そのため、個別に法要をする場合には、僧侶へのお布施として3万円〜5万円、会場を借りる場合にはさらに費用が必要になります。
これらは「永代供養だから無料」とは限らず、供養形式や希望に応じて追加支出となる点に注意が必要です。
納骨料・納骨読経料・彫刻費用などの追加費用
永代供養の基本費用に含まれない項目として、納骨時に発生する費用や読経料、刻字(彫刻)費用などがあります。納骨料は5,000円〜1万円、納骨読経料は1万〜3万円が一般的な相場です。
また、故人の名前を墓誌やプレートに刻む「彫刻費用」は、1件あたり2万〜5万円程度が目安です。石材店が現地で作業を行う場合には、別途出張費がかかることもあります。
このように、基本費用のほかに発生する可能性のある費用項目を把握しておくことで、予算面が安心できます。
永代供養を選ぶ際の注意点と確認ポイント
永代供養は「一度契約すれば安心」と思われがちですが、契約内容によっては追加費用が発生したり、宗派ごとの供養方法に違いがあったりするなど、事前に確認すべきポイントが複数あります。
ここでは、後悔のない選択をするために必要な注意点と、確認しておきたい項目を解説します。
契約前に確認すべき「支払い方法」と「管理期間」
永代供養は一括払いが主流です。しかし、分割払いや定期支払いの仕組みも存在します。
また、個別安置の管理期間(例:10年・33回忌までなど)をすぎると合祀に移行するプランも多いため、「いつまで」「何を」「いくら払うのか」を契約前に必ず確認しましょう。支払いトラブルや「聞いていなかった」という行き違いを防ぐためには、見積書や契約書の文面を丁寧にチェックすることが重要です。
宗派による違い|浄土真宗の「永代経」とは?
浄土真宗では「永代供養」という言葉よりも、「永代経」という表現を用います。これは、亡き人の名を仏前に掲げ、そのご縁により仏法を聴聞するという教義に基づいた営みです。
遺骨の有無にかかわらず、名前だけで申し込むこともでき、必ずしも物理的な埋葬や供養の場を伴いません。一般的な永代供養とは異なる価値観が背景にあるため、宗派によって何を「永代」と捉えるかの違いにも留意して選択しましょう。
安心して任せるために|費用と内容を把握しよう

永代供養に関する費用は、「永代使用料」や「永代供養料」といった基本項目。その他、「年間管理料」「法要費」「戒名料」などの追加費用が存在し、契約内容によってその範囲は大きく異なります。
ここでは、全体像を整理しながら、見落としがちな費用ポイントをチェックします。事前の確認不足がトラブルに直結するケースもあるため、料金体系やサービス内容をしっかりと把握しておくことで、安心できるでしょう。
永代供養にかかる費用は、大きく分けて「基本費用」「毎年費用」「追加費用」の3種類があります。
•基本費用:永代使用料・永代供養料など、契約時に一括で支払う項目
•毎年費用:年間管理料・護持会費など、契約後も定期的に必要となる維持費
•追加費用:納骨時の読経料や、法要・彫刻など希望に応じて発生する費用
これらの区別を明確に理解することで、想定外の出費を防げます。とくに、契約前に費用の明細をしっかりと把握し、不明点はその場で相談することが大切です。
福善寺では、個別で遺骨を預かる「個別納骨壺+手元お参りセット付」「合葬納骨壺」「合葬納骨壺+手元お参り軸付」などわかりやすい永代供養(永代経)の納骨プランがあります。永代供養で心配なことがありましたら、福善寺までご相談ください。