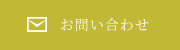永代供養で法事はしなくていい?遺骨の預け先と安心できる選択肢とは2025.06.12 コラム
少子高齢化や家族構成の変化により、お墓の管理や法事の継続が難しくなる家庭も増えています。近年、「永代供養」という選択肢が注目されています。
しかし、「永代供養を選べば法事はしなくてもよい」と考える人がいる一方で、実際には判断に迷う場面も多いのではないでしょうか。
本記事では、永代供養と法事の関係について詳しく解説し、遺骨の預け先や家族の心情にも配慮した安心できる供養のあり方をご紹介します。ぜひ最後までお読みください。
永代供養で法事はしなくていい?その考え方と注意点

永代供養は「遺族が法事をしなくて済む」と誤解されがちですが、実際には状況や考え方によって異なります。ここでは、永代供養を選んでも法事が必要になる場合や、遺族の心情、寺院との関係性を踏まえた対応について解説します。
永代供養の「供養」は法事の代替になるのか
永代供養とは、家族や親族に代わって寺院などが継続的な供養を行ってくれる方法であり、少子高齢化や核家族化が進む現代において注目されています。しかし、「永代供養を選べば法事は不要である」というわけでもありません。
永代供養は主に合祀や納骨後の故人全体に対する管理や読経などが対象です。一方、個別の故人を対象とした年忌法要や法事とは意味合いが異なります。
つまり、永代供養は寺院などに一定の供養をお願いする方法ですが、個人をしのびたいという遺族の気持ちに応えるためには、個別に法要をすることが必要です。また、寺院によっては、遺族の希望に応じて法要を個別に実施できる体制を整えている寺院もあります。
法事の意義と宗教的な背景について
法事は、故人の冥福について祈ることを目的とする仏教儀式であり、遺族が心を整え、故人との精神的なつながりを感じる大切な機会です。仏教では「追善供養」という考え方が根付いており、残された人が供養を行うことで、故人の成仏や来世での安寧が得られるとされています。
また、年忌法要のように特定の節目に供養を行う習慣は、先祖代々の伝統を受け継ぐ行為としても重要な意味を持ちます。現代では形式にとらわれず、気持ちを込めて法事を行うことの意義が見直されつつあるようです。しかし、法事は宗教的な意味にとどまらず、家族の絆を再確認し、心を癒やす貴重な時間ともいえるでしょう。
遺族が法事を行うことで得られる心理的メリット
永代供養を選択する場合でも、法事を行うことで遺族の心に大きな安らぎがもたらされることもあります。法事は単なる宗教的儀式ではなく、故人をしのび、思い出を語ることで遺族同士の絆を感じる場です。
また、定期的に法事を行うことによって、故人との精神的なつながりを保ち続けられるという安心感も得られます。とくに、後悔や悲しみを抱えている遺族にとって、節目ごとの法要は「できることをした」という気持ちを持たせてくれる大切な節目といえるでしょう。永代供養に任せきりにするのではなく、自ら供養に関わることで、心の整理にもつながるのです。
永代供養で法事を行うタイミングと一般的な流れ
永代供養をしても、遺族が希望すれば法事を行うことが可能です。年忌法要や納骨式など、法事のタイミングや流れを知っておくと安心です。
永代供養後に法事を行う主なタイミングとは
永代供養を行った場合でも、節目ごとに法事を希望する遺族は少なくありません。主なタイミングとしては、四十九日、一周忌、三回忌などの年忌法要があげられます。これらの時期は、故人の死と向き合い、遺族が心の区切りをつける大切な節目です。
また、納骨式とあわせて法要を行うケースもあり、葬儀後にあらためて供養の機会を設けることもあります。永代供養では定期的に供養をしますが、個別に法事を行うことで、より故人に寄り添った供養が可能となります。こうしたタイミングを意識しておけば、供養の形にも柔軟性が生まれるでしょう。
法要の一般的なスケジュールと進行の流れ
法要の流れは寺院や地域によって多少異なりますが、一般的なスケジュールには一定の型があります。まず、僧侶による読経が行われ、その後、焼香や法話が続きます。参加者全員で故人について、しのぶ時間を持ち、終了後に会食の場を設けることも少なくありません。
永代供養とあわせて法事を依頼する場合、お寺が式の準備や進行をサポートしてくれるため、遺族の負担は軽減されます。法要の規模や内容は希望に応じて調整が可能で、家族のみで静かに執り行うケースも増えています。法要の流れを知っておけば、心構えができ、当日も落ち着いて対応できるでしょう。
永代供養での法事にかかる費用と相場

法事には読経料・供物代・会食費などの費用がかかります。永代供養と一緒に法事をする場合の費用感や、福善寺のように、遺骨の預かりから法要まで一貫して対応してくれる寺院での事例を参考に、費用の目安を紹介します。
永代供養と法事を併用した場合の費用内訳
永代供養を利用する場合でも、法事を希望すれば別途費用が発生します。具体的には、僧侶への読経料、供花や供物代、参列者への会食代などが主な項目です。読経料は地域で違いがあります。およそ1万〜5万円が目安です。
供物や供花も用意する場合は、あわせて1万〜2万円程度かかることもあります。会食を行う場合、1人あたり3,000〜5,000円が一般的です。
また、福善寺のように、法事を希望に応じて対応してくれる寺院では、柔軟に費用の相談もできます。
施設や宗派によって異なる価格帯
永代供養と法事にかかる費用は、施設の規模や立地、宗派によって大きく異なります。たとえば、大都市にある有名寺院では読経料や供養料が高めに設定されていることが多く、地方の小規模な寺院では比較的抑えられた費用で供養をお願いできる傾向にあるようです。
また、宗派ごとの儀式の違いによっても必要な物品や所要時間が異なるため、費用に差が生じる要因となります。さらに、個別供養を希望する場合や、法要に特別な形式を求める場合には、費用が発生することもあります。事前に寺院と相談することが大切です。
永代供養で安心を得るには?法事の有無と家族の選択

法事をしなくても故人の供養はできますが、残された家族が心穏やかに過ごすためにはどう選択すべきか悩ましいところです。福善寺のように、遺骨の預かりから法要まで一貫して対応してくれる寺院の存在も安心材料となります。
遺族にとっての「安心」とは何か
永代供養を選ぶ際、多くの遺族が求めるのは「安心感」です。これは単に遺骨を預けられるという物理的な意味だけでなく、精神的な満足感や、供養がきちんと行われているという信頼からくるものです。
とくに、日常生活のなかで墓参りや法事を行う時間が取れない方にとって、寺院が継続的に供養してくれる体制は大きな支えになります。
さらに、福善寺のように、希望に応じて法要を行ってくれる環境が整っていれば、家族の気持ちに寄り添った柔軟な対応ができるでしょう。安心感とは、形式的な供養だけでなく、遺族の心に寄り添う配慮の積み重ねから生まれるものなのです。
法事を省略するリスクと後悔しない判断
永代供養を選ぶ際に「法事をしない」という選択をする方もいますが、その判断には慎重さが求められます。法事を省略することで、費用や手間を減らすことはできますが、後になって「やはり何かしてあげればよかった」と後悔するケースも少なくありません。
また、親族間で価値観の違いがある場合、法事をしなかったことがトラブルの原因になることもあります。後悔しない判断をするためには、供養の意味をしっかりと理解し、家族とよく話し合うことが大切です。たとえ簡素な形式でも、心のこもった供養を行うことで、気持ちに区切りをつけ、前向きに生きていく力につながる場合もあります。
まとめ:永代供養で法事はしなくていい?後悔しない選び方とは
この記事では、永代供養で法事をしなくてもよいかどうか、遺族の気持ちや費用面、供養のあり方から考えてきました。永代供養は利便性に優れた供養方法ですが、遺骨の預け先や供養の内容によって、家族の安心感に差が生じることもあります。
福善寺のように、寺院内で遺骨を預かり法要もできる場所を選ぶことで、柔軟な対応が可能になるといえます。永代供養の形は多様ですが、遺族の気持ちに寄り添いながら柔軟に対応してくれる寺院を選ぶことで、より安心感のある供養が可能です。
永代供養の内容や実施先によって、家族が納得できるかどうかは変わってきます。法事の有無を含めて、自分たちにとって後悔のない選択肢を見つけることが、何よりも大切です。