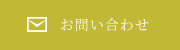浄土真宗の教えに沿った墓じまいと永代供養の進め方2025.04.25 コラム
浄土真宗の門徒として墓じまいを検討されている方へ向けて、本記事では教義に基づいた考え方や手続きの流れを、できるだけわかりやすくご紹介します。
お墓をどうするか迷われている方や、永代供養という選択肢について知りたい方が、安心して判断できるよう、信仰と現代社会との折り合いのつけ方に焦点を当てて丁寧にお伝えしていきます。形式にとらわれず、心を込めた供養の在り方を一緒に考えていきましょう。
浄土真宗における墓じまいの考え方と背景

近年、「浄土真宗 墓じまい」というキーワードで検索する人が増え、現代的な供養のかたちに関心を持つ門徒の存在が浮き彫りになっています。
社会の変化とともに、信仰と実生活のバランスを見直す動きが強まっており、多くの人が現実的な視点から墓じまいを考えはじめているようです。
こうした流れを受け、浄土真宗の教えに基づきながらも、時代に合った供養の在り方を模索する必要性が高まっています。不安や疑問を抱えたままでは前に進みにくいため、教義の基本を確認しつつ、具体的な対応の方向性を整理していくといいでしょう。
墓じまいを検討する背景と現代の事情
現代は、少子高齢化や核家族化の進展により、お墓を守り続けることが難しくなってきました。たとえば、子どもが都市部に移り住んで戻る予定がない、あるいは後継者がいないといった事情から、お墓の管理について悩むご家庭が増えています。
このような背景のなか、「墓じまい」や「永代供養」といった新たな供養の選択肢が注目を集めています。とくに浄土真宗の門徒にとっては、宗派特有の教義や儀式との整合性をどう考えるかが悩みどころになることもあるでしょう。
福善寺では、現代の暮らしに寄り添うかたちで相談を受け付けており、それぞれのご事情に応じた柔軟な対応を心がけています。
浄土真宗の教義と墓じまいへの基本的な立場
浄土真宗では、故人は阿弥陀如来のはたらきによって速やかに極楽浄土へ往生すると教えられています。これは「即得往生」とも表現され、死後に迷うことなく救われるという安心感が信仰の中心にあるからです。
そのため、法要は故人の冥福を祈るためではなく、生きている私たちが仏法にふれ、信心を深める機会として重視されます。亡き人とのご縁を通じて、自分自身のいのちの尊さに気づき、阿弥陀仏への感謝を新たにする。その姿勢が大切とされています。
また、浄土真宗におけるご供養は、形式ではなく、日々のお念仏や法要を通じた仏法の実践という点に特徴があります。
他宗派で行われる「閉眼供養」の代わりに、「遷座法要(せんざほうよう)」が行われるのも浄土真宗ならではです。これは仏具やご遺骨を移動する際、その尊厳を守り、仏さまのお力をいただいて新たな場を整える儀式です。
さらに、一般的な「永代供養」と異なり、浄土真宗では「永代経(えいたいきょう)」というかたちで仏法の護持を願うご供養が行われます。本堂でお経をあげ、教えが代々受け継がれることを願うものです。
宗派として墓じまいを推奨しない理由
浄土真宗を含む多くの宗派では、墓じまいを積極的に勧めることはありません。というのも、墓じまいは信仰の問題というより、家族構成や生活環境、将来の見通しといった現実的な要因に基づいて判断されるべきことだからです。
たとえば、遠方に暮らす子どもにお墓の管理を任せるのが難しい、あるいは年齢とともに墓参りが負担になってきたといった事情は、多くの人に共通する悩みです。宗派の方針よりも、個々の家庭の選択を大切にし、それぞれの事情に寄り添った対応を重視する姿勢が求められます。
浄土真宗にも「宗派の教義として墓じまいは認めない」といった決まりはなく、柔軟な判断が可能です。
福善寺では、どのような状況のご相談であっても、門徒の思いに寄り添いながら丁寧に対応しています。
墓じまいの手順と浄土真宗の注意点

墓じまいは、正しい手順を踏めば宗派に関わらず行えますが、浄土真宗には独自の教えや儀式が存在します。この章では、一般的な墓じまいの進め方とあわせて、浄土真宗ならではの注意点についても整理してお伝えします。
「浄土真宗だから墓じまいはできない」と思い込んでいる方も少なくありませんが、実際には家族構成や生活の見通しに応じて、信仰を大切にしながら柔軟に対応することが可能です。
家族で話し合い、意思を固める
墓じまいの際に最も重要なのは、家族や親族間での丁寧な話し合いです。代々受け継がれてきたお墓をどうするかという問題は、感情的な側面も強く、慎重な対応が求められます。
一人の判断で進めてしまうと、後になって不満が噴き出し、思わぬトラブルに発展することもあります。早い段階から話し合いをはじめ、ご先祖への思いや現実的な事情を共有し、全員が納得できる方向を目指すことが大切です。
福善寺でも、初めて墓じまいを検討される方から、具体的な流れについて知りたい方まで、さまざまなご相談に応じています。
改葬手続きと必要書類の準備
墓じまいを進める際には、「改葬許可申請書」という書類を市区町村に提出する必要があります。これは、現在のお墓からご遺骨を別の場所に移すための正式な手続きで、役所の許可を得たうえで工事などを進めることになります。
具体的には、まず現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を受け取り、移転先が決まっていればその「受け入れ証明書」も準備。この2つの書類をもとに改葬許可を申請し、許可証が交付されたら、ようやく改葬工事が可能になります。
この申請には時間がかかることもあるため、余裕を持って早めに準備を始めることが大切です。不安な点がある場合は、お寺と連携をとりながら進めると安心です。
墓石撤去と新たな納骨先の選定
改葬許可が下りた後は、墓石の撤去工事をし、墓地を更地に戻します。この作業は専門の石材店に依頼するのが一般的で、事前に費用や日程について確認しておくとスムーズです。同時に、ご遺骨の新たな納骨先を決める必要があります。
選択肢としては、納骨堂・永代供養墓・樹木葬・散骨などがあり、それぞれ家族の事情や宗教的な考えに応じて選ばれています。
浄土真宗では、形式にとらわれず信心を重視するため、どの供養方法を選んだとしても、故人への敬意と感謝の気持ちを込めて行うことが大切です。福善寺でも、ご意向に沿った永代供養の方法を案内しています。
遷座法要の実施とお寺への相談
ご遺骨を移動する前には、浄土真宗において「遷座法要」を行うのが一般的です。これは、ご遺骨や仏具を新たな場所に移すにあたり、仏さまにご報告し、その尊厳を保つための儀式です。
他宗派で行われる「閉眼供養」に似ていますが、浄土真宗では「仏さまを閉じる」という概念はなく、あくまで「移動に際して感謝を伝える法要」として位置づけられています。
法要の内容や時期については、お寺と相談しながら進めるのが一般的です。福善寺では、初めての方にもわかりやすく流れを説明し、準備をお手伝いしていますので、安心してご相談ください。
浄土真宗における永代供養の選択肢と供養の実際

浄土真宗では、亡くなった方は阿弥陀如来のはたらきによって、すぐに極楽浄土に往生すると教えられています。そのため、「永代供養」という言葉が持つ一般的な意味とは少し異なる受け止め方をされることもあります。
とはいえ、家族や後継者がいなかったり、お墓の管理が難しかったりする現代の状況に対応するため、実務的な意味での永代供養を取り入れている寺院も少なくありません。
こうした供養は、教義に反するものではなく、「永代経(えいたいきょう)」として仏法を護持する取り組みとされています。福善寺では、本堂での勤行や定期的な法要を通じ、ご遺族が仏縁をつなぎ続けられるよう、体制を整えてきました。
ここでは、形式にとらわれない、心のこもった供養のかたちとして、浄土真宗における永代供養の実際をご紹介いたします。
福善寺の永代供養におけるお参りと法要の利便性
福善寺では、ご遺骨を本堂にお預かりする永代供養を行っており、法要の際にその場でお参りできる環境が整っています。たとえば年回忌法要では、ご遺骨の前でお経をあげられるため、別の場所へ移動する手間がありません。
墓地と法要会場を往復する必要がないため、高齢の方や遠方にお住まいの方にとっても大きな負担軽減になります。ご家族の事情にあわせて柔軟に対応できる点が、好評です。
こうした利便性は、供養を継続するうえでの安心感にもつながり、仏縁を保ち続ける後押しとなっています。
法要の継続で仏縁を保てる
お墓の有無に関わらず、故人をしのぶ気持ちや仏さまとのご縁を大切にすることは、浄土真宗の教えの根本にあります。福善寺では、永代供養においても定期的な法要を通じて、仏法にふれる機会を継続的に作っています。
直接お墓参りができなくても、法要に参加し、お念仏を唱えることで、亡き人とのつながりを感じられることでしょう。形式ではなく、心を込めた実践こそが供養であり、仏さまの教えと向き合う時間として大切にされています。
形式よりも心を大切にする教義と調和
浄土真宗では、仏事において形式よりも「感謝の心」や「故人を思う気持ち」が何より重視されます。そのため、永代供養の方法が一般的な形式と異なっていても、心を込めた供養であれば本質的に問題はありません。
福善寺では、こうした教義にのっとり、それぞれのご家庭の事情や思いにあわせて、柔軟な供養の方法を提案しています。「こうすべき」と決めつけるのではなく、現代に合った供養の在り方を大切にしています。
ご相談はいつでもお気軽に
永代供養や墓じまいに関するご相談は、多くの浄土真宗の寺院で受け付けています。「何から始めればいいのかわからない」「費用について知りたい」「家族とどう話し合えばよいか不安」といった悩みに対しても、丁寧に説明をしています。
浄土真宗の供養の基本は、形式に縛られず、仏さまを敬い、故人を大切に思う心を忘れないことです。まずは信頼できるお寺に相談し、今後の方針を一緒に考えていくことをおすすめします。
浄土真宗の教えに基づいた供養の新しいかたち
浄土真宗の基本的な教えでは、「亡き人は阿弥陀仏のはたらきによって、すぐに極楽浄土へ往生する」とされています。この確かな信仰があるからこそ、墓じまいや永代供養といった現代的な供養の選択肢も、教義と矛盾するものではありません。
むしろ、家族の事情やライフスタイルの変化にあわせて、より心のこもった供養のかたちを選ぶことは、仏縁を保ち続ける一つの方法だといえるでしょう。お墓がある・ないに関わらず、仏さまへの感謝と、故人を思う心があれば、それは立派な供養です。
浄土真宗では、「形式にとらわれず、信心を大切にする」ことが基本です。たとえば、遷座法要や本堂での納骨、定期的な法要といった実践的な方法を通じて、現代の生活に合った供養のスタイルが確立されつつあります。
不安や迷いがある場合は、まずは教義に詳しい寺院に相談し、ご自身やご家族にとって最適なかたちを探ることが大切です。大切なのは、「こうしなければならない」という思い込みに縛られるのではなく、仏さまへの感謝と故人への敬意を忘れずに供養を続けることです。