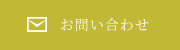永代供養で起こるトラブルとは?後悔しないための選び方と対策2025.04.21 コラム
少子化や核家族化の影響により、お墓の継承や管理が困難になっている家庭も少なくありません。さらに無縁墓の増加や、都市部での墓地不足・価格高騰といった社会的背景から、近年「永代供養」が注目を集めています。
このような状況の中、終活の一環として生前に永代供養を検討する人も増えており、自分の死後に家族へ負担をかけたくないという意識が高まっています。一方で、「永代供養にしたら本当に安心なのか」「トラブルにならないか」といった不安を抱く人も少なくありません。
この記事では、永代供養を選ぶ際に起こりやすいトラブルや注意点を紹介し、安心して供養の形を決めるためのヒントをお届けします。
永代供養とは?基本的な種類

寺院や霊園によって内容や宗派の考え方も異なるため、供養のスタイルや宗派の違いも配慮する必要があります。永代供養について考えるには、その仕組みや種類を知ることが重要です。ここでは永代供養の仕組みや一般墓との違い、永代供養の種類について説明します。
※永代供養の種類についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
→ [永代供養の種類とは?合葬・個別・納骨堂の違いを解説](リンクURL)
永代供養とは
永代供養とは、墓地の管理や供養を遺族に託すことなく、寺院や霊園に管理・供養を依頼する方法です。継承者がいない場合や、家族に負担をかけたくないと考える人々に選ばれています。たとえば、生涯独身の方や子どものいない夫婦が、自分たちの死後に備える手段として選ばれることもあります。
一般墓との違い
一般的なお墓は、家族が代々管理し、定期的に墓参りや清掃、法事をする必要があります。一方で永代供養は、契約時に一定の費用を支払えば、その後は管理や供養を寺院などが担ってくれるため、子孫への負担が大幅に軽減されます。最近では、地方にある実家のお墓を誰も管理できず、永代供養へ移行するケースも多いようです。
永代供養の主な種類(合葬・個別・納骨堂など)
永代供養にはいくつかの形態があります。合葬型は他の方と一緒に納骨される方式で、費用を抑えられる点が特徴です。個別型は一人ひとり専用の納骨スペースに納められ、一定期間後に合葬されるケースもあります。
納骨堂型は室内で管理されるロッカータイプです。天候に左右されず参拝できるのもメリットのひとつになります。永代供養は供養期間や方式、費用に違いがあるため、自身の意向や予算にあわせて選ぶことが大切です。
永代供養で起こりやすい4つのトラブル

永代供養に関するトラブルは、事前の情報不足や認識の違いから起こることが多く、実際に多くの相談事例があります。ここでは、体験談から得られた代表的なトラブル事例を紹介しながら、注意すべきポイントを整理します。
永代供養は便利で現代的な供養方法である一方、誤解や確認不足からトラブルが生じることも多いようです。ここでは、実際に起こりやすい4つのトラブル事例を紹介します。
システムや契約内容の誤解
永代供養は「永久に遺骨を供養してくれる」と思っている人が多いようです。しかし、実際には、一定期間後に合葬されるケースが多く、誤解も生じやすいのが永代供養の契約です。契約内容を十分に確認せずに申し込むと、後々「思っていたのと違う」といった不満が生じることもあります。
たとえば「永代=永久」と思い込み、契約後に「33回忌以降は合葬」と聞かされてトラブルになったという相談もあります。契約書の中に細かい規定が書かれているため、読み飛ばさずにしっかり目を通すことが重要です。
費用や支払いに関する認識のずれ
一括払いが主流とされる永代供養ですが、状況によっては追加費用が発生することもあります。たとえば法要や管理料が別途必要なケースもあり、見積書を確認せずに契約するとトラブルに発展することが少なくありません。
「初回費用だけだと思っていたのに、年に一度の供養料が必要だった」といった誤解から遺族との間で、もめることもあります。契約前に総費用や追加オプションの有無を確認し、書面で見積もりをもらうようにしましょう。
親族間の意見の不一致
永代供養にするか否かは、故人本人の遺志や家族の価値観によって大きく異なります。とくに、先祖代々の墓を墓じまいして永代供養に移す場合、親族間での意見の相違や感情的な衝突に発展することがあるようです。
たとえば、兄弟のうち一人だけが勝手に永代供養を決めてしまい、後から知った親族が激しく反発したというケースもあります。とくに年長の親族は反発することが多く、事前に十分な話し合いが必要です。
墓じまい時の混乱や離檀トラブル
この手続きは「改葬」とも呼ばれ、行政上の届け出や寺院との話し合いが必要になります。現在の墓を撤去して永代供養に切り替える際、寺院から「離檀料(りだんりょう)」を求められる場合があります。
離檀料を巡るトラブルは全国的にも多くあり、事前に寺院と円満に話し合うことが重要です。「ご本尊(お寺から授かった仏像や位牌)を返してもらえなかった」「挨拶に来なかったと非難された」など、思わぬ人間関係の摩擦が生じることもあります。離檀料の金額や支払い義務の有無は、寺院によって異なるため事前に確認しておきましょう。
トラブルを防ぐためのポイント

こうしたトラブルを未然に防ぐには、契約時のチェック項目を明確にし、家族や寺院と十分なコミュニケーションをとることが大切です。以下に、よくある不安や疑問に対するQ&Aを補足します。
Q. 合葬されるのはいつですか?
→ 契約内容によりますが、一般的には33回忌や一定の保管期間後に合葬されることが多いようです。期間は事前に確認しましょう。
Q. 離檀料は必ず支払う必要がありますか?
→ 多くの寺院では「感謝の気持ち」として離檀料を求められますが、法的義務はありません。丁寧に事情を説明し、話し合いで合意を得ることが重要です。
Q. 永代供養にすると法事はできないの?
→ 可能です。多くの寺院では年忌法要やお彼岸の法要などに対応しており、事前に申し出れば個別の対応もできます。
トラブルを未然に防ぐためには、事前の確認や関係者との話し合いが不可欠です。ここでは、永代供養を安心して選ぶために押さえておきたいポイントを解説します。
永代供養の契約前に確認すべきこと
「契約書の内容」「供養の期間」「合葬の有無」「納骨場所の管理体制」など、事前に細かく調べましょう。不明点がある場合は遠慮せず質問し、書面で明記してもらうことが安心につながります。供養期間終了後の遺骨の扱い(合葬・返還不可など)についても確認しておくと安心です。
寺院との丁寧な相談が安心につながる理由
一方的に資料やネット情報だけで判断するのではなく、実際に寺院に足を運び、住職やスタッフとお話しすることが大切です。寺院の供養の方針や姿勢がわかり、信頼できる対応をしてくれるかどうかも重要な判断材料になります。また、実際の供養風景や施設を見学することで、信頼性や雰囲気を体感できます。
家族や親族との事前共有の重要性
本人が納得していても、家族や親族が後から反対するケースも少なくありません。永代供養を選ぶ場合は、事前に親族と情報を共有し、できるだけ合意形成することが円満な永代供養につながります。書面に残すなどして意思を明確にしておくと、誤解や衝突を避けやすくなります。
寺院での永代供養は安心?福善寺の取り組み
永代供養において寺院を選ぶことは、供養の安心感にもつながります。ここでは、福善寺が提供する供養の形や管理体制についてご紹介します。
福善寺での個別納骨と合葬の違い
福善寺では、希望に応じて個別納骨または合葬を選べます。個別納骨では、オリジナルの骨壺にご遺骨を納め、本堂で大切にお預かりします。合葬の場合は、他の方とともに大きな骨壺に納める形式で、特徴は費用面の負担が少ないことです。永代供養の選択肢が用意されているため、ご遺族の希望や予算にあわせて柔軟に対応可能です。
本堂での遺骨管理と法要の特徴
預けられたご遺骨は、本堂という神聖な空間で丁寧に管理されます。また別途ご希望がある場合、年忌法要や春秋彼岸など、節目ごとの供養も福善寺が執り行い、安心して任せられる体制が整っています。法要の日時や内容についても相談可能で、ご家族の都合にあわせた対応が可能です。
法事もお墓参りも同時にできる安心感
福善寺に遺骨を預けることで、法事とお墓参りを同じ場所で済ませることが可能になります。移動の負担が減り、遠方の親族にも配慮できる点から、実用的かつ心のこもった供養ができます。天候やアクセスを気にせず、年配の方でも安心して参拝できるのが大きな利点です。
永代供養で後悔しないために必要な心構え
費用面や供養の負担についても親族で十分に話し合い、納得したうえで決めることが大切です。永代供養を選んだあとに後悔しないためには、事前の準備と心構えが大切です。最後に、選ぶ際に心に留めておきたいポイントを整理します。
以下のポイントを押さえておくと、永代供養の選択で後悔するリスクを減らせます。
•永代供養の形式や契約内容を十分に理解する
•家族や親族と事前に話し合い、納得のうえで進める
•寺院や霊園の対応方針を確認し、信頼できるところを選ぶ
•トラブル事例を参考にし、事前にリスクを把握しておく
•納骨後の供養や管理体制についても調べておく
永代供養は、現代のライフスタイルに合った合理的な供養方法として、多くの方に支持されています。しかし一方で、内容や手続きに対する誤解や、親族間の意見の違いなど、注意しなければならない点もあります。
この記事を通じて、永代供養にまつわる基本知識とトラブルの実態、そして安心して選ぶためのポイントをお伝えしました。ご自身やご家族の将来を考えたうえで、後悔のない選択ができるよう、ぜひ参考にしていただければ幸いです。